「一年の計は元旦にあり」とは?意味や由来・使い方を徹底解説!
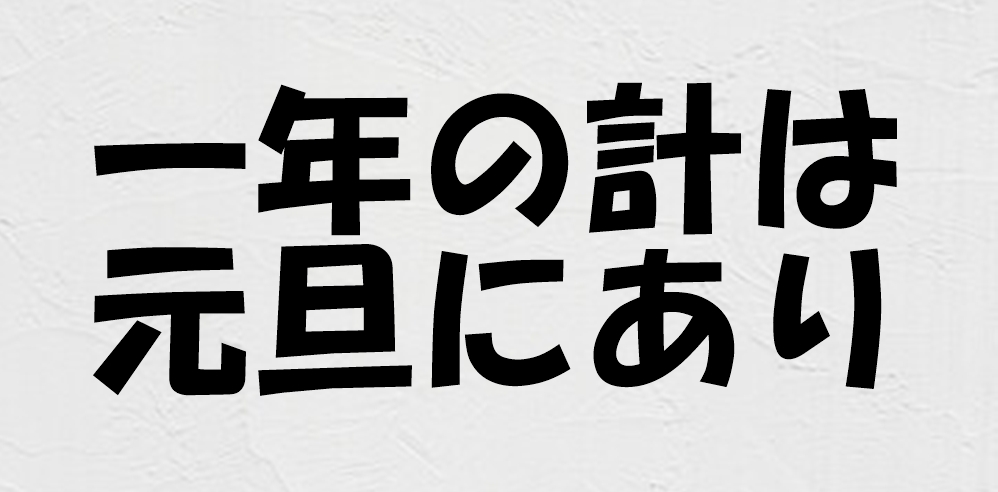
「一年の計は元旦にあり」と言う言葉、良く耳にしますが、実際はどのような意味なのでしょうか。
そこで今回、その意味や由来、使い方など解説してまいります。
「一年の計は元旦にあり」その意味は
「一年の計は元旦にあり」は、一年の目標や計画は年の始め(元旦)に立てるべきで、最初が肝心という意味のことわざです。
新年の最初に方針を決め、それに沿って行動すると良い、という戒めや励ましの言葉として使われます。
由来・ルーツ(どこから来たのか)
このことわざには複数の諸説があります。
中国古典由来説:古い漢文に同様の表現があり、「一年の計は春にあり(=一年の計画は春に立てよ)」という説があります。
毛利元就(日本)説:戦国武将・毛利元就が言ったとされる次の言葉が元になった、という説もあります。

「一年の計は春にあり、一月の計は朔(ついたち)にあり、一日の計は鶏鳴にあり」という趣旨の教えから派生したとする解釈があります。
どちらの説も有力で、江戸期以降の教育者や文学者(例:安井息軒の「三計」など)を通じて日本語のことわざとして定着していきました。
使い方(例文・場面別)
日常、ビジネスや教育などでよく使われます。形式ごとに具体例を示します。
カジュアル(友達へ)
「一年の計は元旦にありって言うし、今年はゲームの大会で優勝するって決めた!」
フォーマル(挨拶文・年頭所感)
「一年の計は元旦にあり。職員一同、今年も目標に向けて邁進します。」
教育・指導(子ども・学生に)
「一年の計は元旦にあり。学期が始まる前に勉強の計画を立てよう。」
ビジネス(会議や年初レビュー)
年始のキックオフで「一年の計は元旦にあり、まずは四半期ごとのKPIをここで決めましょう」
使うときのポイントとして
・年の初めの「決意表明」や「目標設定」のように使うと自然です。
・ユーモアで「今日からやる」場面にも使える例として
「一年の計は元旦にあり…って言ったけど、今日でも遅くないよね?など。
注意・補足

「元旦を過ぎたら遅い」という解釈は正確には不要です。
ことわざとして 「始めに計画を立てることが大事」という点であり「いつでも計画を立てて実行すればよい」と捉えても問題ないのではないでしょうか。
類似のことわざ
① 「一日の計は晨(あした)にあり」「一月の計は朔にあり」年・月・日の“最初”を大事にする考え方。
② 「思い立ったが吉日」――始めること自体を肯定する点で補助的に使えます(元旦にこだわらない場合)。
まとめ
コアメッセージ:「初めにきちんと計画を立てることが、その期間を左右する」。
歴史的には中国古典や日本の戦国〜江戸期の教えが背景にあり、現代では新年の決意表明としてよく引用されます。
