お正月すごろくの語源とは?手作りから学ぶ由来と楽しみ方

お正月といえば、家族や友人とゆったり過ごす時間が楽しみの一つです。
その中でも、昔から日本で親しまれてきた遊びのひとつが「すごろく」です。
おせち料理を囲みながら、みんなで笑い合いながら遊ぶすごろくには、長い歴史と深い意味があります。
ここでは、「すごろく」という言葉の語源から、手作りすごろくを通して学べる文化や楽しみ方まで、くわしく紹介します。
すごろくの語源と起源

「すごろく」という名前の語源には諸説ありますが、
有力なのは、サイコロを振って駒を進める動作や、「双六(すごろく)」という漢字が「双(ふたつ)+六(サイコロの目)」を意味しているという説です。
つまり、「二つのサイコロを使って進める遊び」という意味が込められているのです。
日本にすごろくが伝わったのは奈良時代といわれています。
当時は中国から「盤双六(ばんすごろく)」というボードゲームが伝わり、貴族のあいだで楽しまれていました。

これは現在のバックギャモンに似た遊びで、知的な勝負として人気がありました。
その後、時代が下るにつれ、江戸時代には庶民の間で「絵双六(えすごろく)」という形に発展します。
こちらは、サイコロの目に合わせてマスを進み、「上がり」を目指すという今のすごろくに近い形式です。
内容も「出世双六」「道中双六」「人生双六」など、社会風刺や道徳を取り入れたものが多く、遊びながら教養を身につける役割もありました。
お正月にすごろくをする意味
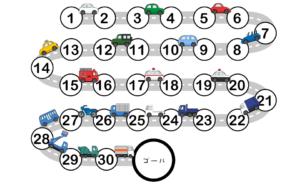
お正月にすごろくをする習慣は、江戸時代から広まりました。
新しい年を迎えるときに「スタートからゴールへ向かう」という流れが、人生の再出発や運試しの象徴とされたためです。
サイコロの出目には「運」や「幸運」という意味合いがあり、「一年の運勢を占う遊び」として楽しまれるようになりました。
また、家族や友人と一緒に遊ぶことで「笑う門には福来る」という言葉どおり、笑いの多い年の始まりを願う意味も込められています。
手作りすごろくで学ぶ文化と楽しみ
近年では、家族や学校で「手作りすごろく」を作ることも人気です。
自分たちでテーマやルールを考えることで、昔ながらの遊びの魅力を体験できます。
たとえば、次のような作り方があります。
① テーマを決める
「一年の目標」「家族の思い出」「旅行」など、自分たちに合った内容を選びます。
② マスを作る
スタートからゴールまでの道を作り、途中に「一回休み」「○マス進む」「質問コーナー」など、工夫を加えます。
③ イラストを描く
マスごとに絵を描いたり、色をつけたりして見た目も楽しく。手作り感が出るほど、遊ぶときの笑顔も増えます。
④ ルールを決めて遊ぶ
家族でサイコロを振って遊びながら、マスに書いた出来事を話したり、思い出を共有したりすると、自然と会話が弾みます。
手作りすごろくの魅力
手作りすごろくの魅力は、単なる「遊び」ではなく、「家族の絆づくり」や「創造力の発揮」にもつながることです。
子どもたちは自分でルールを考えることで想像力や判断力を育て、大人は子どもの発想に触れて新鮮な気持ちになれます。
また、遊びながら「昔の人も同じように笑っていた」という日本の文化のつながりを感じることができます。
お正月の静かな時間に、手作りのすごろくでにぎやかに盛り上がる——そんな光景こそ、日本の伝統的な「家族の正月」の姿といえるでしょう。
まとめ

すごろくの語源は「双六(ふたつのサイコロ)」にあり、奈良時代の盤双六から江戸時代の絵双六へと形を変えながら、日本の文化の中に根づいてきました。
お正月にすごろくを楽しむことには、新しい一年の幸運を願う意味や、家族の絆を深めるという大切な意義があります。
手作りすごろくを通して、遊びの中に込められた歴史や人々の想いを感じ、昔ながらの正月の楽しさを現代に受け継いでいきましょう。
