仕事納めと御用納めとは?知れば得られる意味の違いとは?
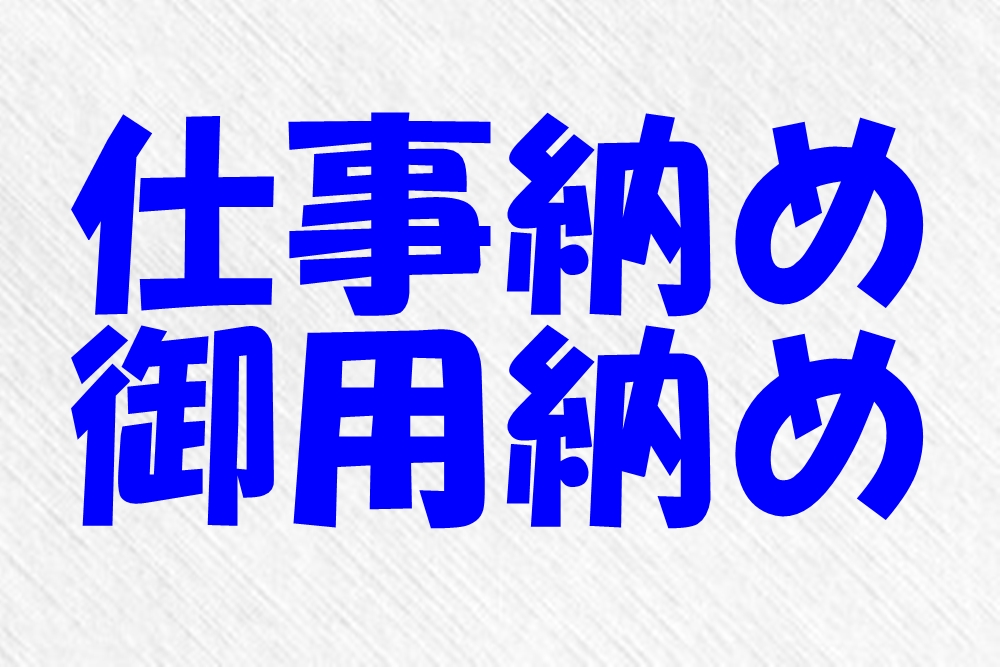
年末になるとよく耳にする「仕事納め」と「御用納め」というのがありますね。
どちらも「その年の仕事を終える日」を指す言葉ですが、実は使われる場面や意味には、はっきりとした違いがあります。
この記事では、知っておくと役立つ「仕事納め」と「御用納め」の違いをわかりやすく解説します。
1. 仕事納め(しごとおさめ)
「仕事納め」と「御用納め」は似ていますが、少し意味と使われ方が違います。
以下で詳しく説明します。
意味
会社や一般の職場で、その年の仕事を終える日のことを言います。
つまり「今年の仕事は今日で終わりです」という日です。
使われる場所
民間企業
商店
学校 など
日にち
多くの場合、12月28日ごろが仕事納めになります。
(※土日が重なる場合、または年度によって前後します)
例文
「今日が今年の仕事納めです。お疲れさまでした!」
「仕事納めの日に大掃除をした」
関連語・仕事始め(しごとはじめ)

意味:新しい年に入って最初に仕事を始める日。
日にち:多くの会社では 1月4日前後(休日の並びによって変動)。
例文:「仕事始めの日に新年のあいさつ回りをした。」
2. 御用納め(ごようおさめ)
意味
官公庁(国や地方自治体の役所など)の仕事を納める日のことです。
つまり、「公務員の仕事納め」を指します。
日にち
法律(行政機関の休日に関する法律)で、
12月28日 が「官庁御用納め」と定められています。
翌年の 1月4日 が「官庁御用始め(かんちょうごようはじめ)」です。
例文
「本日は官公庁の御用納めです」
「役所は御用納めで午後から閉まります」
関連語・御用始め(ごようはじめ)
意味:官公庁などが 新年最初の仕事を始める日。
日にち:1月4日(法律で定められています)
例文:「年明けの御用始めに、庁内で仕事始め式が行われた。」
| 項目 | 仕事納め | 御用納め |
|---|---|---|
| 意味 | 一般企業などのその年の仕事を納める日 | 官公庁(役所)のその年の仕事を納める日 |
| 主な対象 | 会社員・商店など | 公務員・官庁 |
| 日にち | 12月28日前後 | 12月28日(法律で決まっている) |
つまり、
民間 → 仕事納め
役所など公的機関 → 御用納め
という違いがあります。
まとめ
「仕事納め」と「御用納め」は、どちらも一年の仕事を締めくくる大切な日ですが、使われる場面が異なります。
仕事納めは企業やお店など民間の職場、
御用納めは役所などの官公庁で使われる言葉です。
どちらの日も、1年の労をねぎらい、新しい年に向けて心を整える節目の一日。
違いを知っておくことで、年末のあいさつやビジネスマナーでも一歩差がつきます。

