卒業を彩る「蛍の光」歌詞の深い意味を解説
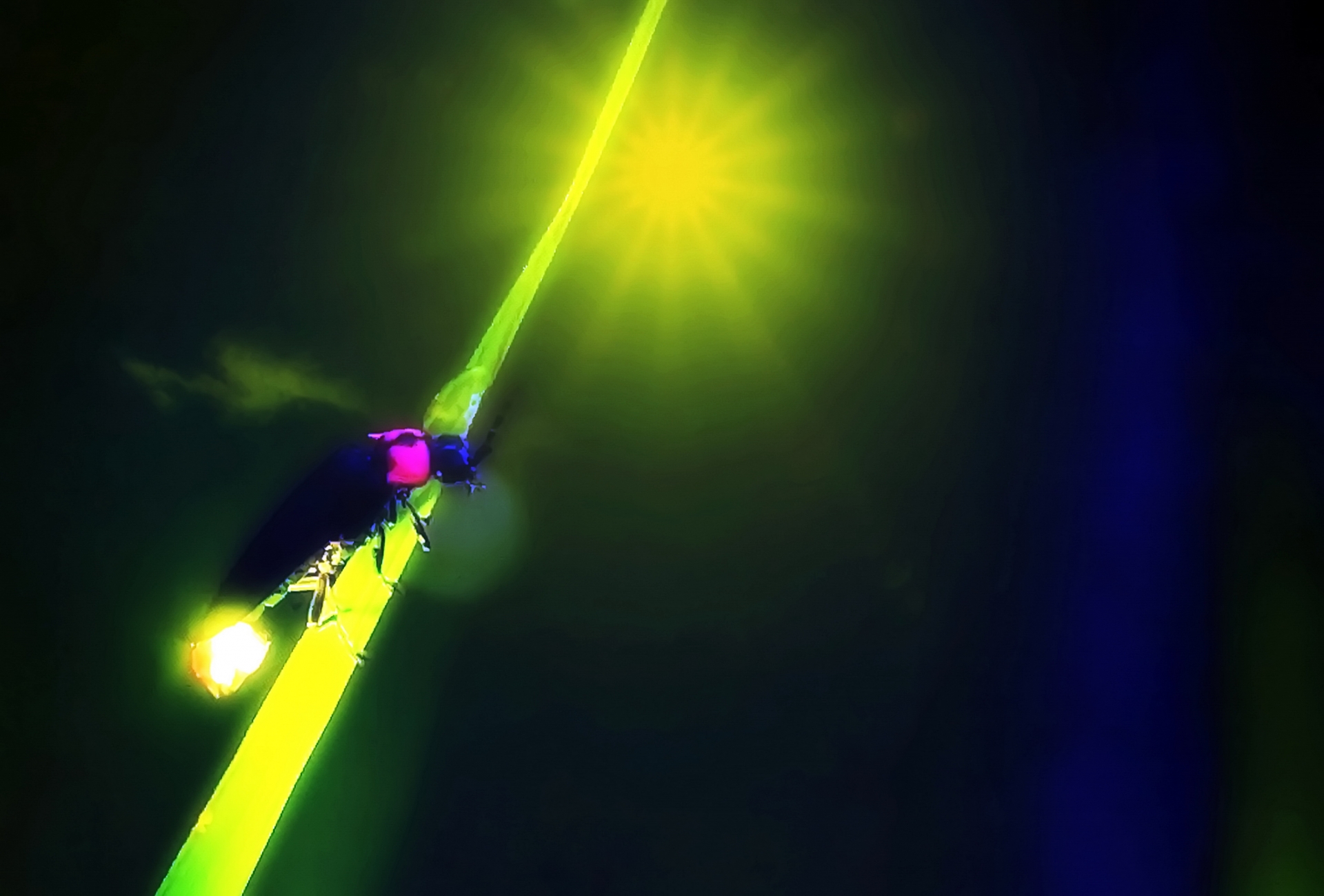
卒業式で歌われる「蛍の光」は、努力や感謝、友情を込めた深い意味を持つ歌です。
その歌詞を読み解くと、別れの歌を超えた人生の教えが見えてきます。
「蛍の光」とは
「蛍の光(ほたるのひかり)」は、日本で卒業式や閉会行事の定番として歌われる唱歌です。
明治時代に作られた曲で、別れや門出を象徴する歌として長く親しまれてきました。
歌の由来
原曲:スコットランド民謡「オールド・ラング・サイン(Auld Lang Syne)」
新年の歌や友情の歌として世界中で歌われています。日本への伝来:明治14年(1881年)、文部省唱歌として日本語の歌詞がつけられ、学校教育に広まりました。
卒業式で歌われる理由
努力と学びの象徴:勉強に励んだ日々を振り返る歌詞が、卒業にふさわしい。
別れと門出の歌:仲間や先生との別れ、新しい人生への一歩を表す。
伝統性:明治時代から長く歌い継がれ、どの世代にも共通する「卒業の歌」として定着。
「蛍の光」の役割

卒業式のフィナーレ
卒業証書授与や式典の最後に斉唱され、会場全体を感動で包む。閉店ソングとしても使用
百貨店やスーパーの閉店時間に流れることで有名。「お別れ」の象徴的な曲になった。文化的遺産
学校教育や日常生活で広まり、国民的な歌として定着する。
卒業を彩る「蛍の光」
卒業式で歌う「蛍の光」は、単なる別れの歌ではなく、
学んだ日々への感謝
師や友との別れ
未来への希望と決意
を込めて歌われるものです。
この歌が流れると、教室や体育館に過ごした日々の思い出がよみがえり、涙を誘う「卒業の象徴」となっています。
歌詞の内容と意味
◆1番

歌詞の内容
蛍の光や窓に映る雪の光を頼りにして、夜遅くまで学問に励んだ様子を描写しています。
深い意味
「蛍の光」:中国・晋の「車胤(しゃいん)」が、家が貧しく灯りが買えなかったため、蛍を袋に集めて光で勉強した故事を表しています。
「窓の雪」:同じく中国・孫康(そんこう)が、雪の反射光で学問に励んだ故事を指します。
→ つまり、貧しい環境でも知識を求め努力した人々の姿を通じて、学びへの情熱と忍耐の大切さを歌っているのです。
◆ 2番
歌詞の内容
学校で学んだ年月が過ぎ去り、先生から受けた恩を忘れてはいけない、と説いています。
深い意味
「ときは移り」:学んだ日々は過ぎ去り、卒業や人生の節目を迎えること。
「師の恩」:学問だけでなく、人としての道を教えてくれた先生への感謝。
→ これは 師弟関係の大切さ、恩を忘れない日本的な精神 を強く伝えている部分です。
◆ 3番
歌詞の内容
国を守り、世のために尽くすことを誓う内容です。
深い意味
「身を立て 名をあげ」:自分の志を成し遂げて立身出世すること。
「国に尽くし」:学んだ知識や力を、社会や国家に役立てること。
→ 近代国家として歩み始めた明治時代の教育理念を反映しており、学びは自分のためだけでなく、世のために生かすものという価値観が込められています。
◆ 4番
歌詞の内容
遠く離れたとしても互いに心を通わせ、再び会える日を願う歌です。
深い意味
「千島(北海道)や沖縄」など広い地域を挙げ、仲間が日本全国へ散っていくことを暗示。
「会うべき」:いずれまた再会しようという友情と希望の表現。
→ 卒業での別れを越えて、友情の絆や連帯感が永遠に続くことを願う部分です。
◆ 総合的な深い意味
「蛍の光」は単なる「別れの歌」ではなく、
努力の尊さ(1番)
恩師への感謝(2番)
社会への貢献(3番)
友情と再会の希望(4番)
という流れを持ち、人生の節目にふさわしい 「学びから社会へ巣立つ決意の歌」 となっています。
まとめ

「蛍の光」は、学びへの努力や恩師への感謝、社会への貢献、そして友情と再会への願いを歌い上げた、卒業にふさわしい一曲です。
その歌詞に込められた深い意味を知ることで、卒業式での歌声はより心に響き、人生の節目を彩る大切な思い出となるでしょう。

