喪中はがきはいつ出すべき?郵便局の切手でマナーを整えよう
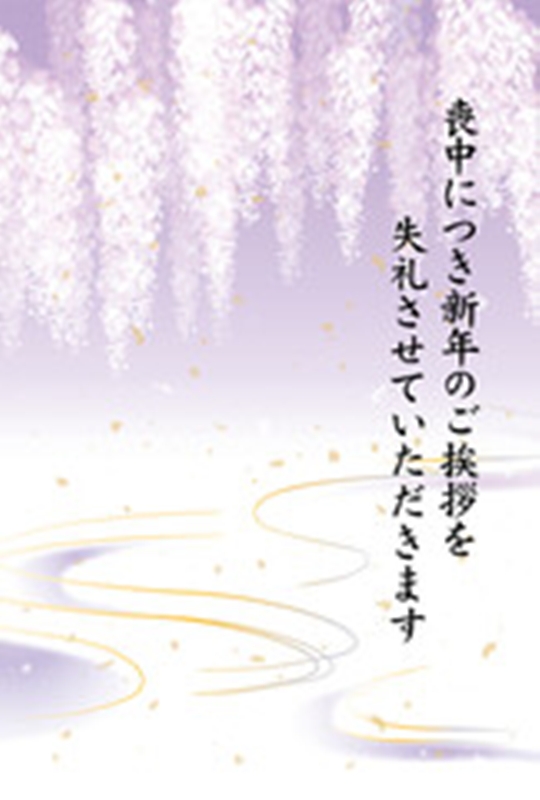
喪中はがきは、大切な方を亡くした際に、年賀状による新年のご挨拶を控えることをお知らせするものです。
出す時期や使う切手にもマナーがあり、とくに郵便局で用意されている弔事用切手を選ぶと、より丁寧な気持ちを伝えることができます。
そこで今回、喪中はがきを出すタイミングや切手のマナーなど解説してまいります。
出す時期の基本
喪中はがきは、年賀状の準備が始まる前に相手に届くように出すのがマナーです。
日本郵便では年賀状の引受開始が 12月15日 なので、それより前(11月下旬~12月上旬)に届くのが理想です。
1. 理想的な投函時期

11月20日頃から12月10日頃までに投函すると、先方にちょうどよい時期に届きます。
遅くとも 12月20日頃までには相手に届けたいところです。
2. 時期別の具体的な対応
春~秋に不幸があった場合
余裕を持って準備できるので、11月下旬~12月初旬に投函すれば十分間に合います。
11月に不幸があった場合
急いで準備する必要があります。できれば12月10日頃までに出しましょう。文面は簡潔でよく、詳細を書かなくても問題ありません。
12月中旬以降に不幸があった場合
年賀状のやり取りがすでに始まっているため、喪中はがきではなく、年明けに「寒中見舞い」で訃報と年始の挨拶を兼ねて伝えるのが適切です。
3. 出す相手
基本は 普段年賀状をやり取りしている相手全員になります。
喪中はがきは「年賀状を遠慮します」という通知なので、日頃からやり取りのない相手に無理に出す必要はありません。
4. 出すのが遅れてしまった場合
12月下旬になってから喪中はがきを出すのは失礼にあたる場合があります。
その場合は、年明け(1月8日頃~立春の前日まで)に「寒中見舞い」として知らせるのがマナーです。
喪中はがきに切手が必要な場合とは

喪中はがきは通常、私製はがき(自分で用意するはがき)に印刷して使うことが多く、その場合は切手を貼る必要があります。
郵便局の「喪中用はがき(弔事用はがき)」を購入すると、最初から弔事用切手が印刷済みなので、切手を別に貼らずにそのまま投函できます。
1. 喪中はがきに使う切手のマナー
喪中はがきは弔事に関する郵便物なので、切手のデザインや色に配慮が必要です。
適した切手(弔事用切手)
郵便局では「弔事用」として、落ち着いたデザインの切手が用意されています。
胡蝶蘭(白)
清らかで上品なイメージを持つ花。定番で安心して使えます。山百合など
慎ましく気品ある花で、弔事にふさわしいデザインです。
これらは郵便局の窓口やオンラインショップで販売されています。
避けた方がよい切手
鮮やかな花柄や金色など、お祝い事を連想させるデザイン。
キャラクター切手や記念切手など、カジュアルで明るい印象のもの。
弔意を示す目的なので、落ち着いたトーンの切手が望ましいです。
2. 弔事用切手の使い方のポイント
はがきの宛名面にきちんと貼る
→ 傾いていると失礼に見えるため、まっすぐに。不足金額がないか確認
→ はがきや往復はがき、または封書にする場合は料金が異なるので注意が必要です。郵便局でまとめて購入・相談できる
→ 窓口で「喪中はがきに使う切手」と伝えれば、弔事用切手を案内してもらえます。
3. 喪中用はがき(郵便局製)の利用
郵便局では、印刷済みの「胡蝶蘭」デザインのはがきが販売されています。これを使えば、切手を貼る手間が省け、マナー違反の心配もありません。
宛名や文面を印刷してそのまま投函できるため、手軽で安心です。
まとめ

喪中はがきは、相手が年賀状を準備する前の11月下旬から12月初旬に届くように出すのが一般的です。
切手は郵便局で販売されている弔事用を選ぶと、より丁寧な印象を与えられます。時期と切手のマナーを整えることで、相手に失礼のない心遣いを伝えることができます。

